
研究の背景と目的
環境汚染は invisible killer とも呼ばれています。経済とのトレードオフによって、顕在化されない環境汚染は着実に進行しており、WHO では、大気汚染だけでも年間 900 万人の「早過ぎる死」を引き起こしていると警告しています。環境汚染の大きな発生要因の一つは急激な開発であり、その 92%は低中所得国で生じています。特にアフリカ諸国では予防の基盤となる科学的データ構築が遅れています。
我々は、これまでのザンビアにおける調査研究で、鉱山から住宅地への汚染メカニズムおよび拡散範囲の解明、汚染された土地の植生回復と農地としての再利用法の構築、オンデマンドな環境修復手法の開発、汚染による人の健康および社会経済への影響の定量化を推進しており、これらの研究成果により、社会実装としての問題解決に進むための道筋が構築されつつあります。環境汚染問題を解決するためには、真の意味での異分野連携が必要であり、我々は、農学、工学、保健学、経済学、獣医学、地球環境学、理学、教育学、情報科学の専門家でその解決に取り組んできました。一方で、環境汚染物質によって人や動物、植物の生体内で何が起こっているのか、明らかにされた化学物質は意外に少ないのです。古典的な重金属の鉛やヒ素、農薬 DDT やダイオキシン類でさえ、実はその毒性のメカニズムは根本的には解明されておらず、実際の環境下のばく露レベルで人や動物にどのような影響があるのか、わかっていません。前述した「環境汚染物質による早すぎる死」についても、環境汚染物質がどのように影響しているのか明らかにした研究はありません。その原因は、実験室内での研究とフィールド状況下との乖離であり、また人の非侵襲試料の限界でもあります。現在、毒性学では、化学物質の分子レベルからフィールドレベルまでのメカニズムと影響をとらえる AOP(Adverse Outcome Pathway)コンセプトが浸透しつつありますが、AOP コンセプトの最後のピース、すなわちフィールドにおける研究結果が組み込まれている環境汚染物質は、正確には未だありません。また、AOP の先、すなわち明らかにされた毒性によりどのような社会的・生態学的影響が起こるのか、この観点を毒性学に持ち込んだ実践的研究はありません。
研究内容
我々は、これまでに構築して来た異分野連携チームにより AOP コンセプトを超え、「SocialToxicology」「Predictive Toxicology」の概念の下、環境汚染物質により何が起こりどのような解決が必要となるのか、予防的な視野を含めた新たな研究概念を提案します。これを成し遂げるために、経済学や工学、農学、保健医学・疫学、動物進化学・遺伝学、情報科学の専門家と組み、さらに人と動物の垣根をなくした医学的研究、Zoobiquity(汎動物学)により、動物をモデルに環境汚染物質が人の次世代への個や群に与える影響に重点を置いてそのメカニズムと現象を明らかにします。今年度はコロナ禍により、海外への渡航が制限されている状況を見越して、環境汚染のモデル地域として、人と動物について豊富な試料を北海道大学で有しているザンビアを設定し、鉛汚染のフィールド調査と影響のシミュレーションに関する研究を実施します。当然、本研究はザンビアや重金属汚染に限るものではありません。どのようなデータがシミュレーションに必要かを明らかにし、様々な環境汚染物質において、人・動物における環境汚染影響のフィールド研究と毒性メカニズムの解析と、次世代への影響メカニズムと予測を行う研究を水平展開するための基盤を構築します。
詳細はこちら
研究チーム構成
- 獣医学研究院 教授 石塚 真由美(代表)
- 獣医学研究院 准教授 池中 良徳
- 獣医学研究院 准教授 中山 翔太
- 保健科学研究院/環境健康科学研究教育センター 教授 池田(荒木) 敦子
- 獣医学研究院 研究員 中田 北斗
- 地球環境科学研究院 助教 早川 卓志
- 獣医学研究院 特任准教授 山崎 淳平
- 農学研究院 准教授 内田 義崇
- 工学研究院 教授 五十嵐 敏文
- 工学研究院 准教授 伊藤 真由美
- 経済学研究院 准教授 樋渡 雅人
- 情報科学研究院 准教授 小川 貴弘
- 千葉大学 予防医学センター 助教 江口 哲史
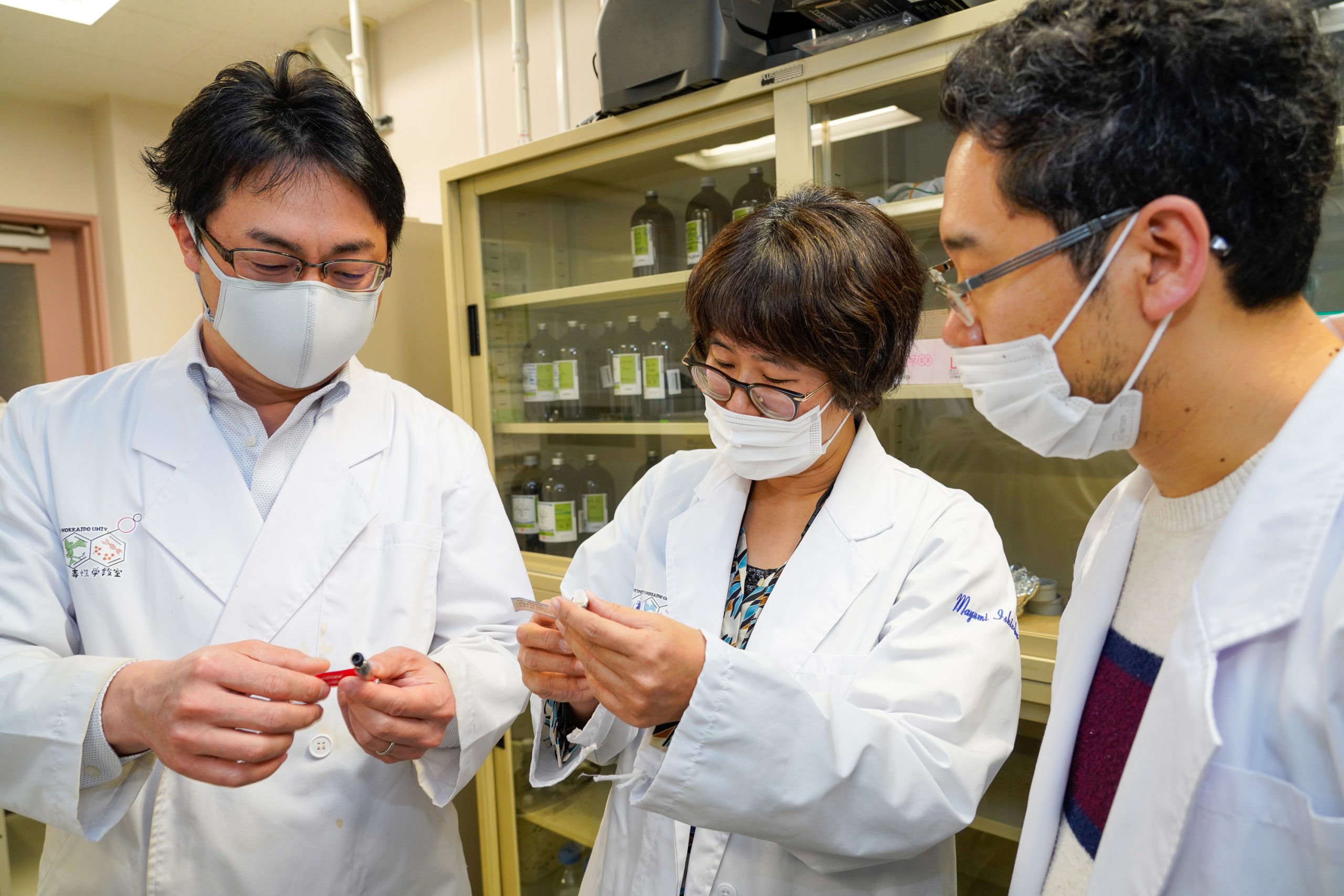
実績報告
- 令和2年度実績報告(実績報告書・実績概要)
- 令和3年度実績報告(実績報告書・実績概要)
- 令和4年度実績報告(実績報告書・実績概要)
- 令和5年度実績報告(実績報告書・実績概要)
